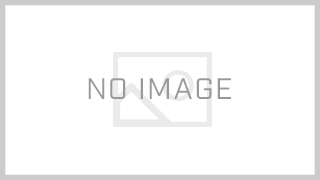1989年8月18日から8月29日まで、旧ソ連を訪問しました。主にその時のことを書きたくなり、ブログを始めることにいたしました。ウクライナに平和が訪れることを心よりお祈りいたします。
まだブログの書き方がよくわからないままのため、今回は、2度目の訪ソ(1990年8月22日~31日)の時の体験を「第一回日ソ学生会議・和文報告書」から公開し、これから順番にブログの体裁を整えていきたいと思います(時間をかけてゆっくり取り組む予定です)。
二泊三日・緊急入院レポート
私は、とても元気な人間である。滅多なことで、貧血なんて起こしたこともなかった。しかし、連日のハードスケジュールのため疲れていた上に、時間がなく、二食も抜いてしまったのが間違いの始まり、いや、結果としては良かったのかもしれない。
KGBの博物館で、私は何年ぶりかの、しかも倒れそうなほどひどい貧血になってしまった。椅子に座っても楽にならず、ソファに寝て、ようやく治ったのであった。治って「ああ、よかった」と思ったころ、医者が助手を二人も連れてやってきた。脈と血圧を測って、さらに薬を飲ませてくれた。何の薬だかとても気になったが、後で貧血のための薬と聞いて、少し安心した。もう治ったのに診てもらっても仕方がないと思っていたら。いきなりタンカに乗せられて救急車に乗り、病院へ連れていかれてしまったのであった。
ただの貧血なのに救急車に乗せられるなんて、おかしくて声を立てて笑ってしまった。後で聞いた話だが、その時のドクターも救急車もKGBのものだったそうである。きっと、外国人でKGBのドクターに診てもらって、その上にKGBの救急車に乗ったのは、私だけではないだろうか。おまけに、その救急車は黄色だったそうだ。
病院に着くと、そのままタンカで部屋へ運ばれた。天井しか見えないので、周囲の様子はよくわからない。女の先生がいて、KGBのドクターと話し知多。ロシア語なので内容は全くわからない。モスクワ大の代表の一人が付き添って来てくれたのだが、彼が二人の先生と話して通訳してくれたところによると、私は入院しなくてはならない、ということだった。念のために検査をするので、一日だけ、または、検査の結果によっては二日位の入院が必要であるということであった。自分の体のことくらい自分で良くわかる。単に貧血を起こしたぐらいで入院なんてとんでもない。こんなに元気なのに。何度そう言っても、彼が何と先生に言ったかはわからないが、入院することになってしまった。こんなに元気なのだから明日は退院だろう、一日位面白そうだし、疲れていたので入院も悪くないだろうと、あきらめることにした。
費用はどれくらいかかるのか、と聞いたら、通訳してくれた彼も、ドクター達も、助手の人達も、皆んな笑い出してしまった。「すべて無料ですよ。食事も、もちろん無料です。安心して。」と彼は言った。どうやら、この国では医療費は無料らしい。
カルテのようなものを書き終えて、KGBのドクターと助手二人は帰ってしまった。ドクターは、「大丈夫だよ」とロシア語で言って、にっこり笑った。
さて、その部屋の女医さんは血圧と脈を診て、色々と細かく症状を聞いた。助手の女の人が、採血するからと、万年筆のペン先のような物で、ブスッと中指の先を刺して血を採って行ってしまった。あまりにも痛くて驚いてしまった。指の先から血を採るとは、これも文化の違いなのか、と変わった体験をしたことを楽しむ余裕も出てきた。
それから、他の女医のおばあさんが来て、また血圧と脈を測って、手術の必要はないわね、と言った。私は何度も言うようだが、ただの貧血である。こんなことで入院してしまった上に、手術されては笑い話では済まない。変わった体験だ、などと言っている場合ではなくなってきた。
次にタンカで別の部屋に運ばれた、天井の色が水色だった。前の部屋はクリーム色であった。天井しか見ていないので部屋のことは、それ位しかわからなかった。そこでは心電図をとってもらった。
次の部屋はピンクの天井だった。カルテはどんどんと厚くなっていった。また、脈と血圧を測った。どの先生も脈と血圧を測るのはなぜだろうか。カルテを見れば書いてあるはずである。この後も何人も先生が変わるが、KGBのドクター以外すべて女性のお医者様であった。そして、どの先生も血圧と脈を測って、始めから症状を聞くのであった。何人もの医者で一人の患者を診るということは、良い方へ考えるならば、誤診を防ぐということなのだろうか。
そして、タンカに乗って、車に乗り、別の棟へ。エレベータにタンカごと乗って、部屋に連れて行かれた。6人部屋だった。ここで私は今夜寝るのであった。肥ったおばさんやおばあさんが5人、すでに寝ていた。入って左の真ん中のベッドに私は移された。
また違う女医さんが来た。同じ検査をしていった。しばらくすると、食事が運ばれてきたが、大学の食事とそれほど変わらない内容であった。それからすぐに付き添いの学生は帰ってしまい、私はロシア語もわからないというのに、一人ぼっちになってしまったのである。
つづく